執筆日 2025/02/17
今回は、縦書きで「!」や「?」を書く時に気をつけなくてはいけないルールについて、歴史も交えて書いていきます。
前回も縦書きの基本的なルールとして「段落」について書きました。
どちらも記事内では “ルール” として紹介していますが、あくまでより良くするための一つの方法として捉えていただければと思っています。
出版社にもっていけば色々言われることはあるでしょうし
ネットで調べても、「ルールを守ってない作品を見つけると気になってしまう」という意見もあります。
ですが
ルールはあくまで読者が読みやすくなるように今までたくさんの小説家たちが積み上げてきた知恵です。
守らないから小説の価値が下がるわけではありません。
しかし、価値は変わらないけれど、読んでもらえなくなる可能性はあります。
せっかく書いた作品が、読みづらさのせいで内容を楽しんでもらえないのは悲しいので、先人の知恵を吸収して良い作品を作ろう! ということです。
こだわりがあってこのルールを使いたくない方、良いと思います。
ただ、こだわりがある方も、無い方も、とにかく読みやすくしたい方も、まずはなぜそんなルールが出来たのか知ってから自分がどんなところをこだわりたいのか、どんな文章を書きたいのか考えて、納得のいったものは試してみても良いのではないでしょうか。
知ること、考えることほど、物語を作るために必要なことはありませんから。
「!」「?」の歴史
「!」……ビックリマーク、エクスクラメーションマーク、感嘆符
「?」……はてなマーク、クエスチョンマーク、疑問符
いくつかの呼ばれ方があります。
ビックリマークは1400年ごろ(14、15世紀/室町時代)に、印刷された書物に初登場しているようなのですが、その書物の作者がいきなり使い始めたというわけでは無いと思います。
(もちろん、その人がめちゃくちゃ面白い人でいきなり驚きの表現を使い始めた可能性もある)
それより古い書物は時間の流れによって失われてしまい、現在確認できる一番古いものが1400年の印刷物だというふうに考えたほうが良いでしょう。
日本の書物でも、平安時代(794~1185年/8~12世紀)に書かれた紫式部の源氏物語は、現在本物は残っていません。本物というのは、紫式部が実際に書いたもの、という意味です。
今残っているのは、本物を書き写したものです。
それだけ、過去書かれた書物が現在残っているということはめずらしいのです。
つまり、地球上でビックリマークをいつ誰が使い始めたか、本当のことは分かりません。
では、次に気になるのは、日本語の小説ではいつから使われるようになったのかということですよね。
日本の小説で感嘆符が登場するようになったのは
明治時代 二葉亭四迷、尾崎紅葉などが使っていたことが分かっています。
前回の記事で、「段落」は明治時代に日本の文章に取り入れられるようになってきたと書きましたが、感嘆符や疑問符も明治時代なのです。
ちょっとした文章の決まりを知るだけでも、文明開化の気配を感じられて楽しいですね。
縦書きで「!」「?」を使うときのルール
「!」「?」を書く時
・全角で打つ
・記号の後に句読点「、」「。」はつけない
・記号の後に文章が続く場合は空白1文字あける
・記号の後に記号「……」「──」が続く場合は空白なし
・行頭に「!」「?」を持ってこない
箇条書きにした内容を一つずつ簡単に説明していきます。
全角で打つ
全角は!です。
半角は!です。
ちっちゃいでしょ?
記号の後に句点「。」はつけない
この記事でもその方式で書いていますが「!」や「?」は、句読点と一緒には使えません。
「!」「?」があれば、句読点を付けなくても文章の区切りだと分かりますから、更に句読点をつけてしまうと重複している感じになります。見づらいし意味がありません。
Wordで文章を作成している人は試しに打ち込んでみるとWordからの「間違っているよ!」忠告である赤い波線がでてくると思います。
記号の後に文章が続く場合は空白1文字あける
これは読みやすさのためのルールだと思います。
句点と近い役割と上の説明で書きましたが、「!」や「?」は、言葉の区切りになりますので、区切りを分かりやすく見やすくするために、びっくり! したあとは空白をあけましょう。
「。」や「、」はそもそも小さくて隅っこによっているので空白をあける必要はありません。
記号の後に記号(「……」「──」)が続く場合は空白なし
「!」「?」の後は空白をあけましょうと書いたばかりですが、小説でキャラクターがびっくりした後に気持ちをためたい時は、空白はいりません。
私もこのルールは今、書きながら調べ直していて知りました。
例:「嘘でしょう……? 私は、私は!──信じて、いたのに……!」
という表記が良いようです。
そもそも空白が読みやすさのために作っているものですから
「……」や「──」という記号は視覚的に他の文字より詰まっていませんので、わざわざ空白をあける必要が無いのかもしれません。
行頭に記号を持ってこない
感情の表現としてあえて行頭につける場合を除いて、縦書きの上のマスに「!」「?」「、」「。」が来るのは避けましょう。
しかし文字数の都合で、勝手にそういう表示になってしまうこともあるかと思います。
解決策としては
少しこまめに改行をする。
もしくは文章を書いているソフト、アプリなどの設定を変えてみましょう。
私が愛用している「TATEditor」デスクトップ版では
「表示」→「簡易設定ウィザード」→「禁則処理を使用」にチェック
これで自動的に「!」などが行頭にこないようにしてくれます。
文章を書くためのアプリやソフトでは最初からこの設定になっていたり、変更できたりする場合があるので確認してみましょう。
おまけ1 言葉の調べ方
今回、感嘆符や疑問符がいつから使われるようになったのかを調べました。
正直なことを言うと、そんなこと知らなくても小説は書けます。
私も感嘆符の由来なんて記事を書くために調べていて知りました。
なぜ知らなくても良いことを書くのかと言えば、縦書きのルールが無駄なものを押し付けているわけではないことを知ってほしいからです。
なぜルールが出来たのかを考えること、知ることは大切です。
そして、今回の記事でルールや歴史について知ったあなたがもし新しく言葉の歴史について疑問を持った時に調べやすくなるように、おまけの内容を書いてみました。
今回のように
「この言葉っていつから使われるようになったの?」
ということを知りたい時の、調べ方の紹介です。
ネットで調べたい語句にプラスして「歴史」「由来」「語源」などで検索してみるのもいいですが、もっと詳しく正確な情報が知りたい時、小学館の『日本国語大辞典』が役に立ちます。
日本国語大辞典には、その言葉が最初に登場した文章が載っています。
ただ、紙の書籍で揃えようと思うと全13巻、20万円くらいかかります。
ありがたいことにデジタル版が出ていて、「ジャパンナレッジ」という辞書、辞典サイトで読むことが出来ますが、ジャパンナレッジはお安いコースで月1500円ちょいかかります。
使えるようになる辞書の数を考えれば十分お得ですが、小説を書きはじめたひとが使うには少々荷が重いのが現実だと思います。
大学生だと、大学図書館が契約してくれていて無料で使用することが出来るかもしれません。
また、高校などでも学校によっては契約しているところもあるようです。
自分の所属している施設が契約しているかどうか調べてみましょう。
買うのも難しいし、契約するのも難しいし……という方
公共図書館であれば紙の日本国語大辞典はたいてい置いてあると思います。
近所の図書館のホームページに資料検索機能があると思うので「日本国語大辞典」と入力してみましょう。
ちなみに私はネットでちょこちょこ調べて、時代考証なんとなく大丈夫そうだなと思ったら使っています。
物語の重要な題材や面白そうなことなどは論文を読むこともありますが、基本的にはゆるいです。気負いすぎて書けないよりは、そのくらいでも良いのかもしれません。
こだわりたい場合は頑張って調べて下さい。
おまけ2 昔の小説を手軽に読む方法
今回の記事に登場した二葉亭四迷と尾崎紅葉、読んだことがなくても名前は聞いたことがありそうな二人です。
二人とも青空文庫から無料で作品を読むことが出来ます。
二葉亭四迷を例に検索方法から順に説明!
「青空文庫 二葉亭四迷」検索
↓
「作家別作品リスト:二葉亭 四迷」クリック
↓
「公開中の作品」欄から気になる題名をクリック
(外国人の著者名が書かれているものは、二葉亭四迷が翻訳した作品)
↓
下までスクロールして「ファイルのダウンロード」欄から
「XHTMLファイル」のリンクをクリック
↓
すぐ読める!
青空文庫は、著作権が切れた作品を無料で読めるようにデータとして公開してくれているサイトです。
少し昔の作家で、気になっている作品があったらまず青空文庫で検索してみましょう。
ちなみに、二葉亭四迷は明治時代に活躍した作家ですので、少々むずかしい文章になっています。
漢字にはルビが振られていますが、読み方が分かっても意味が分からない言葉がたくさんあると思うので、無理せず雰囲気だけ味わってブラウザバックしても良いと思います。
どうしても内容を知りたい時は、先にあらすじなどを検索して、なんとなく分かったうえで読み始めても良いかもしれませんね。
私は有名な『浮雲』も読んでいません。まだ興味が湧いていないので。
さて、今回の記事は以上になります。
次回も引き続き縦書きのルールを紹介していきます。
小説で特にセリフなどによく使われる「……」「──」こういった記号について、色々と調べながら、便利機能の紹介なども含めてまとめていこうと思います。
気になる方はぜひブックマークしてお待ち下さい。

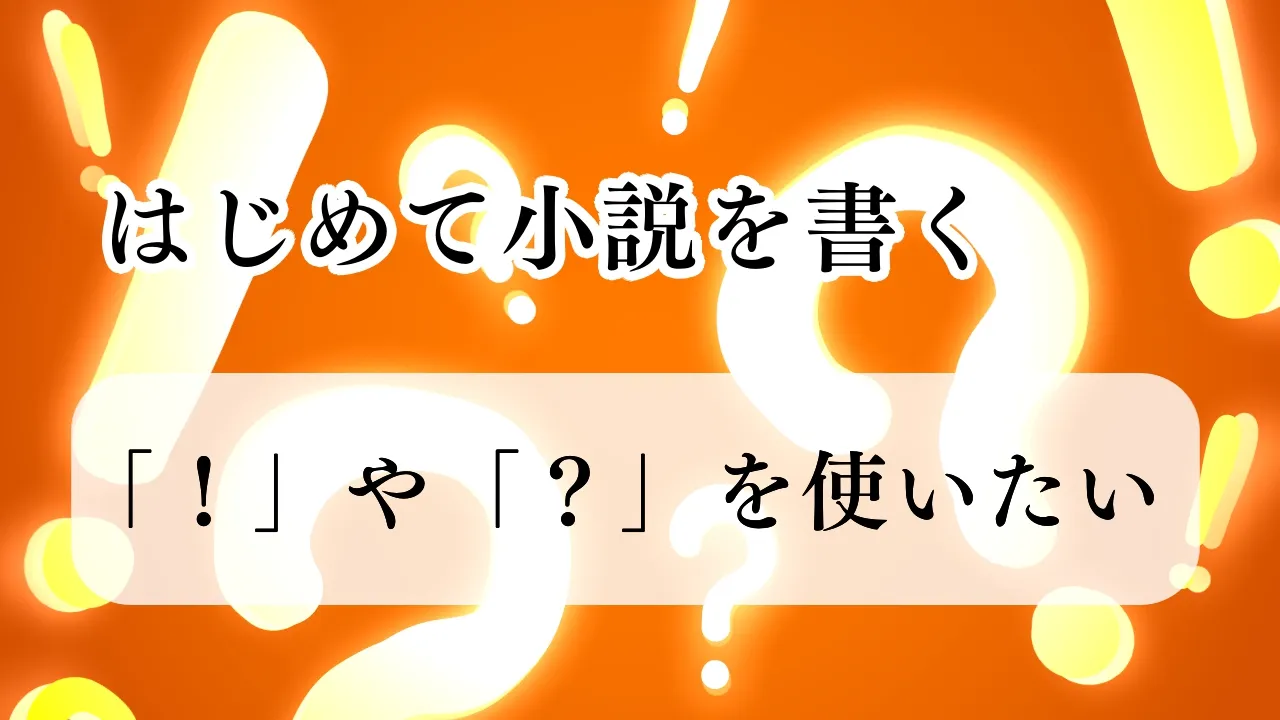

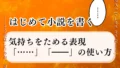
コメント