執筆日 2025/02/25
今回は、小説を書くときに気をつけなくてはいけない誤字について書いていこうと思います。
日本語って難しいですよね。
国語の授業を受けていても、大人になっていざ文章を書いてみようと思うと正しい漢字や正しい意味が分からないこともあります。
間違っていると気づかないまま使ってしまうこともしばしば……。
小説を書くなら誤字脱字、表記揺れはご法度です。
それだけで、小説の世界観から意識が離れてしまったり、間違って伝わってしまったり、そもそも間違いは無いに越したことはないのです。
けれども、私はけっこう色々と間違えながら書いています。
そこで、私がよく間違えている日本語を6つ紹介していきます。
ぜひこの記事を読んで、はじめて小説を書くというあなたも、自分の書いている日本語が正しいか気にしてみて下さい。
微妙に違う 「始」「初」
「始」「初」この漢字は読み方も意味もよく似ていますよね。
でも、正確には少し違います。
意味と使い方の例を見てみましょう。
初めて(はじめて)
まだやったことないことをやる
例:初めて小説を書く(今まで書いたことがなかった、新しい挑戦)
始めて(はじめて)
その行動をやり始める
例:小説を書き始める(書くという行動を開始する)
他にも色々な読み方はありますが、間違えやすいのは「はじめて」を漢字にしたい時ですよね。
使い分けを考えてみましょう。
「初」は経験に意識を置いていて、「始」は行動に意識を置いているという感じでしょうか。
例:私は、初めての小説を書き始めた。
この例だと、小説を書くという経験は初めてであること、そして今から「初めての小説」を書くという行動を始めることが分かります。
また、「書き始める」という行為には「書き終わる」という行為がセットになります。何時間か集中して書いたら、その日の小説を書く時間は終わりですよね。
でも、「初めて書く」という経験は、期間ではなく最初の地点を指しているので、「終わり」はセットになりません。
「初めて小説を書く」とセットになるのは「最後の小説」、もしくは「最期の小説」になるでしょう。もう二度と小説を書かない場合です。
どうでしょうか。少し「始」「初」のことが分かってきましたか?
「初」はとてもややこしいので、他の使い方も少しだけ紹介しますね。
「初」は、時間帯が早いことを表すこともあります。
例:初日(しょにち)、初夏(しょか)
「初」は読み方も多く、小説で使いそうなものをあげてみます。
例:見初める(みそめる)、初(うぶ)、初々しい(ういういしい)
ちなみに「初」は「はじめる」「はじまる」とは読みません。
この2つの読み方は「始」の時に使うものです。
もし「初める」と書いてあれば「そめる」と読むのが正しいでしょう。
「初まる」は、予測変換で「初」が出てこないのでかなり珍しい使い方と言えますが、小説の中で意識的に使うことは可能だと思います。
その場合、読み方はあえて書かないか好きなルビを振ってはどうでしょう。一般的な使い方ではないので「本気」に「マジ」というルビを振るような当て字と同じ感覚で良いと思います。
正しい使い方を知ったうえで、自由に創作をしましょう!
文字一つまで意味を込められるのが文章を書く醍醐味ですから。
似ているけど違う 「辞める」「止める」
「辞める 止める 違い」「辞める 意味」「止める 意味」で調べてみたのですが
なんだか違いがはっきりしないのです。
この記事を見ているあなたも、はっきりさせたくて色々な記事を読み漁っているのかもしれません。
「辞める」 読み:やめる
「止める」 読み:やめる、とめる
問題なのは「やめる」を使う時、何が正しいかということです。
「辞める」
職業に関することをやめる場合に使います。また、「じ」とも読むので、「じ」という熟語が当てはまる場合の物事は「辞」で良いのではないでしょうか。
例:仕事を辞める=辞職する
「止める」
職業関係以外だいたいなんでも使って良いことになっています。
こちらも熟語を当てはめて考えてみましょう。
例:運動会の開催を取り止めた=中止
例:図書館で食べ物を食べるのは止めて下さい=飲食禁止
さて、2つの意味の違いは分かりました。
次はなぜこの2つがややこしくなっているかという事です。
「止める」は、「とめる」という読み方が適切で「やめる」と読むのは常用漢字には載っていないのです。そのため、新聞などでは「やめる」という言葉に「止」は使いません。
けれども、「辞める」は職業に関する場合に使うのが一般的で、それ以外の「やめたい時」に何を使うのが正しいか分からなくなってしまうのです。
平仮名を使えば良い? その通りです。公的な文書、お仕事メールの場合は平仮名にしちゃいましょう。解決です。
しかし小説を書く時、ここはどうしても漢字が使いたい! ということもあるでしょう。
私はあります。
その場合は、先程の例のように、当てはまる熟語を思い出してみたり、常用漢字に載っている読み方を無視してみたりしましょう。
熟語の例で他のものを出してみると「辞世の句」と言ったりするので「こんな人生やめてやるぜ」というセリフが書きたいなら、職業関連とは言えない場合でも「辞める」を使って良いかもしれませんね。
けっこう違う 「対照」「対象」「対称」
あまり頻繁に使う言葉ではないかな、と個人的には思います。
3つの意味はまったく違うものですが、読み方が同じなのと漢字が被っていることもあって、いざ使おうと思うと混乱してしまうことも。
例を見ながら意味を覚えましょう。
「対照」
物事を並べて比べること、照らし合わせること、違いについて説明したい時に使う
例:対照実験を行う/二人は対照的な性格をしている
「対象」
特定の物事を指す
例:彼はこの実験の対象者になっています/この小説は子どもを対象にしているので分かりやすい表現を心がけています
「対称」
シンメトリーであること、ある地点を中心として鏡合わせのような状態
例:左右対称/この建物は噴水を中心に対称になるよう作られている
なにが違うの 「せざるを得ない」「せざる負えない」
「せざる負えない」は間違いです。
正しい使い方を覚えるために言葉を分解して意味を考えてみましょう。
「せざる」というのは「しない」という意味です。
「見ざる、言わざる、聞かざる」という言葉が「見ない、言わない、聞かない」という意味になるように、「ざる」というのは否定的な意味があります。
「得ない」というのも「否定」の意味を持ちます。
「要領を得ない返事だ」という言葉は「要領(要点、大事な部分)が分からない返事」という意味になります。
「せざるを得ない」は、その2つを合わせた言葉。
つまり「しない」ことを「否定」しているので、「しないわけにはいかない」=「本当は嫌だけどやる」という意味になるのです。
ちなみに
「負えない」という言葉は「無理、お手上げ、どうしようもない」みたいな意味です。
例:手に負えない暴れん坊だ、私たちにそこまでの責任は負えません
どれも否定的な意味なので混乱してしまいますが
「せざる」を「得ない」のが正解で
「せざる」「負えない」は、間違いです。
接続詞が必要だと覚えておくと良いかもしれませんね。
ややこしい送り仮名 「話し」
「はなす」と書く時は「話す」ですよね。迷いません。
でも、「はなし」と書く時「話し」なのか「話」なのか混乱します。
調べてみると
「話し」は動詞、「話」は名詞と出てきます。
でも動詞とか名詞とかなんか習ったけどよく分からないし、ぶっちゃけ副詞とか品詞とか他にも色々あった気がするし、見分け方とか覚えてないし、と思ったので頑張って考えてみました。
「話し」
「話す」が変形したもの、つまり喋っている動作を表します。
例:これから話しますので聞いて下さい=「話す」という行動を予告している「話し」
例:私は話しています=「話す」という行動を継続している「話して」
「話」
「はなし」と読むのは、喋っているわけではなく、特定の物を指しています。
例:校長先生の話が長い=校長先生が喋っている行動ではなく、その話の部分を指す。
例えば
「昔話を話し始めた」の場合、「昔の物語」という物を「話す」行為を始めたということになるわけです。
うっかりミス 「以外」「意外」
私が一番よく間違えている誤字です。
なぜならどちらもよく使うので、予測変換で打ち込んでそのまま気づかないのです。
みなさんもよく使う言葉ほど気をつけて下さいね!
注意喚起のために今回の記事に取り入れましたが、せっかくなので意味についても説明しておきます。
「以外」
そのものを除いたもの
例:ネギ以外はいれちゃっていいよ/私以外は部屋に入らないで
「意外」
予想と異なること
例:このネギ意外と辛くないよ/意外と冷静なんだ
「はじめて小説を書く」シリーズは今回で終わりです。
次の記事までに少し時間がかかってしまうかもしれませんが、今後も小説を書き始めたばかりの方、煮詰まっている方のために記事を書いていく予定です。
今のところ、物語の作り方案内として、プロットの作り方、キャラクターの作り方についての記事や、人に読んでもらいたいと思った時にどんな方法があるのかなどを、私自身を例にあげて書いていけたらと思っています。
それでは最後に私から、小説をかきたいと思ったあなたに向けて激励を書いて終わりにしたいと思います。
どれだけたくさん小説を読んでいても、ネットや本で使い方を学んでも、実際に書いて試してみると、上手くいかないことばかりです。
メチャクチャでも良いので書き始めてみましょう。文章にしてみましょう。
頭の中にあったものを吐き出すだけで変わるものがあります。
それを自分で読み返すと、少しだけ客観的になれるかもしれません。
立派な文章でなくて構いません。
書こうとする行為が、私たちの頭を動かします。
この記事が、ここまでたどり着いて、時間を使って最後まで読んでくれたあなたの栄養になってくれることを祈っています。

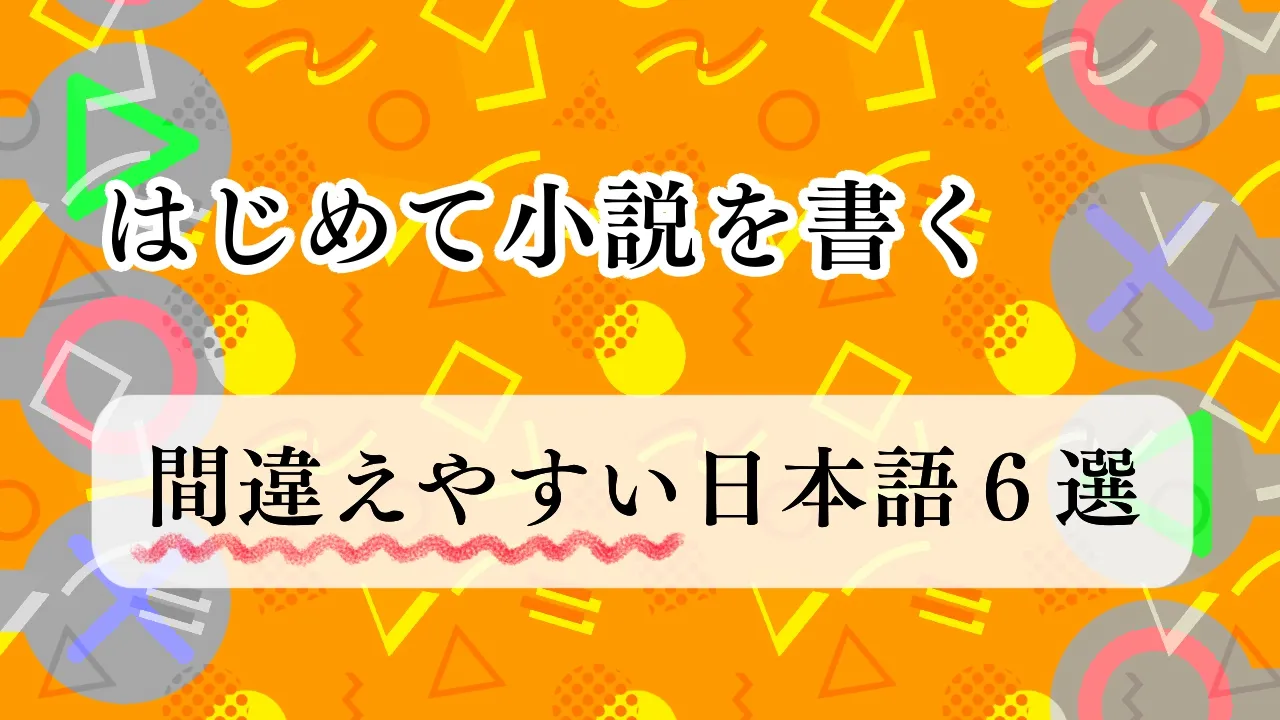

コメント