執筆日 2025/02/14
今回は縦書きのルールのひとつ「段落」について、その必要性や、歴史、小説を書く時に気をつけると良いことなどを書いていきます。
ちなみに
縦書きの基本的なルールは、私自身も色々な記事を読みながら学びました。
色々な人が分かりやすくまとめた記事はネット上に山程ありますので、情報を取りこぼしたくない方は2、3個の記事を読むことをオススメします。
そのうえで、この記事で得られるものがあってほしいと思ったので、私はルールの説明だけでなく、それがいつ出来たのか、なぜそれをする必要があるのか、調べたり考えたりしたことをまとめていきたいと思います。
縦書きのルール 段落について
今読んでいるこの文章のように、文の書き始めに一文字空白を作ることです。
横書きでも縦書きでも改行したあとは1字下げが基本的なルールになっていますが、横書きで書かれたウェブサイトの多くはこのような空白は使っていないと思います。
なぜなら、読みづらいからです。
段落は本来、文章のまとまりを分かりやすくするためのものですが、ウェブサイトは紙の文章と違って改行や空白行が頻繁に入れられます。
この性質と段落は相性が悪いのです。
試しに新しいタブを開いて今まさにあなたが知りたいことである「段落 ルール」などを検索して出てきたサイトを見てみましょう。
おそらく読みやすいと感じるサイトは文章が細かく区切られていると思います。
紙ではなく、ネット上で文章を掲載する場合、あまりにも文章量が多くミチミチ詰まっていると読んでもらえないのです。
あなたもそういうサイトはなんだか難しそうだな、とか、面倒くさそうだな、と思って途中で読むのをやめていませんか?
手軽さがネットの便利なところなのに、さっさと欲しい情報だけ手に入れたい、と感じると思います(こんな欲しい情報以外も長々と書いているような記事を読んでくれてありがとうございます)。
改行の多いネット記事で、ルールに従って改行のたびに1字下げを行っていると下のようなデメリットがあります。
デメリット
・段落が多くなってしまい、文章の頭(左はじ)がデコボコして読みづらい
・1行に書ける文字数が減ってしまい、スマホなどで見る場合読みづらい
改行の本来のメリットである読みやすさが無くなり、文章のまとまりが分かりやすいというメリットも、ネット記事ではそもそも空白行で文章のまとまりがとても分かりやすくしてあるので、意味がありません。
というわけでここからは段落を作らずに続きを書いていきます。
段落を付ける意味
学生時代、国語の時間に段落について習った時
「形式段落」 「意味段落」
なんて言葉を聞いた覚えはありますか?
私はこの記事を書くために調べ直していて思い出しました。きっと習ったのでしょうが記憶の彼方です。
調べてみたところ
形式段落……全ての1字下げがこれに当たる、文章のまとまりを作る
意味段落……文章の内容から考えて意味に変化がある段落のみがこれに当たる
つまり
形式段落はある程度読みやすくするための工夫として文章のまとまりごとにつける段落で、意味段落は文章の内容が変化する時に区切りとしてつけられるものだと思います。
段落の名称は覚えなくていいですが、どんな時に段落を使うのか知っておくと、小説を書く時に役立つと思います。
実際に小説を書く時にどのように役立つかは、段落の歴史を少し紹介してから書いていこうと思います。
段落の歴史
知らなくても困らないことをじゃんじゃん紹介していきます。
なぜならその方が面白いという感情と一緒にルールも覚えられるかもしれないから!
それに、生きていて無駄だと思ったことが活かせるのが小説を書いていて嬉しいことだと私は思っています。今は無駄に思える知識も頭の片隅に置いておくと役に立つかもしれません。
とはいえ限度があるので忙しい人は読み飛ばして下さい。
さて
段落が使われるようになったのは明治時代から
もっと昔の平安時代のしゃらしゃらした文字が書かれている源氏物語などを調べてみると、段落は一切ありません。
「源氏物語 文章」などで画像検索してみて下さい。
頭の文字は横一列きれいに揃っています。
これは
日本語の文化として段落というものは無かったということです。
日本語の文章で大事にされている気がするのでちょっとびっくりですよね。
では、なぜ明治時代から段落が使われるようになったのか?
文明開化です!
明治時代に入り、外国の文化が入ってきて、外国の文章が入ってきて、そこで日本人は「パラグラフ」を「段落」という言葉で表すようになりました。
英語の文章ではずっと昔から段落が存在しています。
それが日本語にも取り入れられるようになってきたのです。
だから、実のところ日本語の段落の歴史は浅く、ルールと言ってもそれほど厳格なものとは言いづらい……とはいえ、やはり長い文章を書くにはあったほうが読みやすいことは間違いないでしょう。
参考
村越行雄2015「段落とパラグラフの構造と方法について」
https://atomi.repo.nii.ac.jp/record/1363/files/atomi_com9_02.pdf。
内容が少しややこしく、ページ数も多いのであくまで参考として載せておきます。
小説で段落を使う時に気をつけること
ここまで色々と段落について話してきて、段落とは文章を読みやすくするためのものだということは分かったかと思います。
では実際に小説で使う時はどんなことを考えながら使ったら良いのでしょうか?
形式段落と意味段落という、それぞれの使い方を参考に段落を使うタイミングを考えていきましょう。
(正式な学校などで教わる「形式段落」「意味段落」の定義とは異なる場合があります。あくまで小説を書く際の一例としてお読み下さい)
形式段落
使い時:一文が長くなって読みづらい時
書き方:改行+1字下げなど
文章の内容に大きな変化がなくても、読みやすさのために段落をつけることも大切です。
出版されている小説を読んでみると想像以上に段落が使われていることに驚くかもしれません。
段落だけに注目して自分の好きな小説を軽く読み直してみてください。
意味段落
使い時:場所・時間・視点などの変化
書き方:改行+1字下げ、改行+空白行+1字下げ
意味段落は、内容の変化、つまりキャラクターのいる場所が変わったり、時間が変わったりする時に段落が変わります。改行をしたあと場合によっては空白行を用いることもあるでしょう。
その他の段落
使い時:強調
書き方:改行+空白行+1字下げ
形式段落、意味段落以外でも、小説を書く時は強調のために段落をつけることがあると思います。
この場合、場面は変わっていない、また文章が長くなっているわけでもない、ということがあります。
それでも “このセリフは大事!”とか、“このシーンは記憶に残したい!”ということがあれば段落はじゃんじゃか変えて、空白行も使って良いのではないでしょうか。
ただ、やり過ぎると返って強調が分かりづらくなってしまい、単にめちゃめちゃ隙間の多いまとまりのない小説になってしまいます。
ここぞという時に、少しモニターから離れて文章全体を見ながら、空白の割合を考えて段落や空白行を用いると良いでしょう。
とはいえ、いきなり良い感じに段落や空白行を作るのは難しいです。
最初のうちは迷走するのが普通だと思うので、今回の記事は最後に少しだけ私が小説を書き始めたころの話をして終わろうと思います。
書きはじめた頃にありがちなこと 筆者の体験談
私は、初めて書いた小説の原稿は既にデータを修正してしまい、完全に最初の頃のものは残っていません。
ですが、記憶をたどると初めて書いた時は本当にひどいものでした。
確か段落は存在していたのですが、空白行がゼロ。
約1万5千字の小説で、5章に分けてあり、データは分割して保存してありました。
一番多いのは一章で5千字、この5千字で一回も空白行が無いとなると、かなり文字が詰まっている感じがして読みづらいです。
そして、空白行が無いと読みにくいことに気づいた私は、今度は大量の空白を使うようになりました。
やはりデータは残っていないのですが、スッッッカスカでした。
形式段落でも空白行を使い、意味段落では2、3行の空白行を使い、さらに強調したい分では4、5行の空白行を使う……という感じだったと思います。
当然、読みづらいです。
ですが、そこから私がそれなりにまともな段落を使えるようになるには2年かかっています。
その間、段落をつけすぎたり空白行をあけすぎたり、無さすぎたり、迷走しながら少しずつ成長してきました。
そんな私が
今から小説を書き始める人に伝えたいのは、迷走して欲しいということです。
迷走しているというのは、より良いものを書くために色々なことを考えている証拠だと思います。
新しい技法を知ったら試して、やりすぎて、というのは、成長しようとしているから起こることではないでしょうか。
全く迷走せず、確固たる完成のイメージがあってそれを最初から表現できるのも素晴らしいと思いますが、そんな人はあんまりいないと思うので、安心して迷走して下さい。
どれだけネットや本で、小説の書き方を勉強しても、自分で試して迷走してこそ身についていくものだと思います。
私の記事が、あなたの迷走の良い友となれることを祈っております。
今回の記事は以上になります。
このブログでは、今後も歴史や豆知識、作者の体験なども交えた様々な小説の書き方、作り方を紹介していきます。
次回は「!」「?」など記号を書く時のルールについてまとめようと思うので気になる方はぜひブックマークしてお待ち下さい。

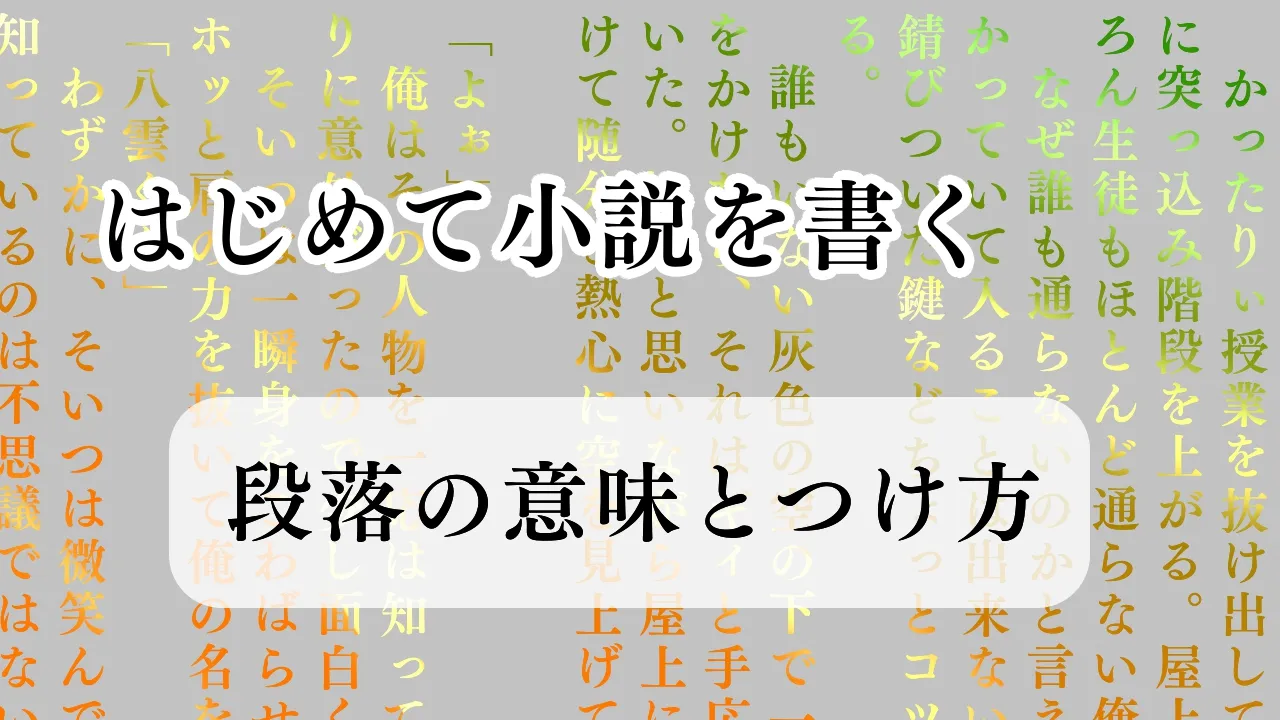
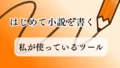
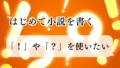
コメント